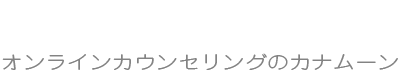古代人の死生観
古代人の死生観

オンラインカウンセリングのカナムーンです。
持病のために定期的に通院している医院に行くと、待合室に置かれている『一個人』という雑誌を手に取ることが多くあります。神社やお寺、お城や古墳など私の好きな特集を組んでいることがあり、いつも楽しみにしています。
9月号の特集は「死ねない時代の仏教入門」です。日本の文化は、縄文文化と仏教が融合してできたものであると河合隼雄さんは言っていましたが、まさにその通りであると思っています。私は仏教のなかでも、釈迦の教えが一番好きです。日本に伝わってきた仏教は、中国の儒教や道教が加わった在家信者を中心とした大乗仏教なので、少ししっくりこないところがあります。
釈迦は、自らが死にゆく姿を見て侍者のアーナンダが嘆き悲しんでいるときに「かつて説いたはずではないか。愛するものから別れなければならない時が訪れることを。生じたものはいずれ無くなるのだということを」と教えています。そして、釈迦は観察ができない死後の世界のことは語らなかったといいます。
同号のなかで私が最も心を惹かれたのは「万葉集の挽歌にみる古代人の死生観」です。それは、仏教が日本に伝来する前の日本人の死生観はどのようなものであったのかということに、とても興味があったからです。挽歌とは死を悼むために詠まれた和歌で、仏教の影響力が強まってくると同時に、一気に減少していったようですよ。
この挽歌について、高桑枝実子さんは次のように説明しています。古代日本人にとって肉体は魂の容れ物で、意識不明に陥った状態のときには、肉体から魂が出たり入ったりを繰り返していると考えられており、生と死との境が曖昧でした。そしてこれらはすべて死者の魂の意志による移動で、魂が完全に肉体から離れてしまうと「死に至る」とされていました。そして、挽歌は不安定な状態の魂を肉体へ呼び戻すための呪術的な手段として詠まれていたというのです。
例えば、近江天皇が病気のときに大后が詠んだ和歌「青旗の 木幡の上を かよふとは 目には見れども 直に逢はぬかも(巻二・一四八)」には、近江天皇の魂は見えるけれど、直接はお逢いできないと書かれています。こうして和歌を詠むことで、何とか魂をつなぎ止めておこうとしたようです。この挽歌は当時の死葬儀礼の一つで、これらの挽歌が仏教の読経に変化していきました。
縄文文化と釈迦が好きな私としては、挽歌を詠むことで死者の魂を送り出す死葬儀礼のほうがしっくりきます。愛するものを送り出すために、我が心の中で生じている事象を和歌にして詠むことで、改めて自らを知ることができるのではないかと思うのです。誰かの読経ではなく、自らの言葉で愛するものを送り出したい気がします。融合が得意な日本人としては、お経をマスターして、和歌とともに送り出すのもいいかもしれませんね(笑)。
with k 4E #456