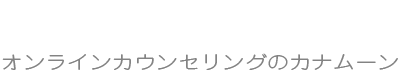椿
椿

オンラインカウンセリングのカナムーンです。
今回の写真は内モンゴル出身の女性が送ってくれた六甲山の椿の写真です。赤い椿の花言葉は、「控えめな素晴らしさ」「謙虚な美徳」ですが、まさに彼女にぴったりな花言葉です。写真のアングルからも、厳しい冬を終え、これから春を迎える希望のような謙虚さを感じることができます。素敵な写真をありがとうございます。
椿から連想するものに、椿油があります。温暖な気候の地域で自生する椿からとれる椿油は、毛髪や全身のオイルとして使われてきました。この椿油は家具の手入れに使われることもあります。私は東京にいた時に美術関係の仕事をしていましたが、そこは広葉樹の一枚板のテーブルのギャラリーも兼ねていて、壁には一枚板がずら~っと立てかけられていました。その一枚板の手入れに使っていたのが椿油でした。
一枚板のテーブルはすべてが広葉樹です。広葉樹というのは、その名の通り広くて平べったい葉を持っています。枝分かれして丸くこんもり育ちます。組織構造が複雑で細胞の種類が多いので、空気を通す穴が少なく、硬く重い材質になります。20万種類以上の樹種があり、暖かい地域で育ちます。国産の広葉樹には、欅(ケヤキ)・楢(ナラ)・タモ・栓(セン)・桐(キリ)・栗(クリ)・楡(ニレ)・撫(ブナ)・楓(カエデ)・橡(トチノキ)・桂(カツラ)・山桜(ヤマザクラ)・楠(クスノキ)・朴(ホオノキ)・胡桃(クルミ)などがあります。私は栓・栗・胡桃の木目が好きでした。
神社などに自生している広葉樹は太くて立派な木が多いのですが、このような木が寿命を迎えたり、さまざまな理由で伐採された時に、オークションのような形で売りに出される時があります。そこに家具の工房などが買い付けにいき、何年もかけて乾燥させ、木目が綺麗に見えるように裁断して、一枚板の家具にするのです。無垢材として漆やオイルで仕上げて、テーブルなどにします。横幅が1メートルを超えるものは、百万円から数百万円というお値段がついていきます。私はそれらの一枚板に囲まれながら仕事をしていました。
“三百年生きてきた木は、三百年使える家具に”というキャッチフレーズで、東京の南青山にギャラリーを構えていました。一枚板のテーブルになっても、木は呼吸しています。部屋が乾燥していたら水分を出してくれますし、湿気ていたら水分を吸ってくれます。この一枚板を手入れする時に、椿油を使っていたのです。贅沢でしょう?
このギャラリーは、雑誌の取材で使われることも多く、西島秀俊さんや大沢たかおさんなどがいらして、インタビューを受けていたことを覚えています。もう25年以上前のことですが・・・。
「休」という字はにんべんに木と書きます。人が休む時には木が必要なのですね。そういえば、「一本の実のなる木を描いて下さい」と教示するバウムテストという描画テストがあります。バウムはドイツ語で木という意味です。木は人が立っている様子と似ているので、その人が描く木によって心の内面を窺い知ることができるというものです。このように見てみると、私たち人間にとって、木はなくてはならないものなのだな~と改めて感じることができました。
with k 4E