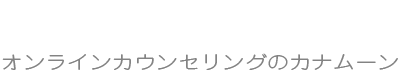船形埴輪
船形埴輪

オンラインカウンセリングのカナムーンです。
写真は松阪市の宝塚古墳から出土した日本最大規模の船形埴輪のレプリカです。実物は、全長140cm、円筒台を含めた高さ94cm、最大幅36cmと見応えがある大きさでした。実物の写真はSNSでの投稿を禁止されていますので、ロビーの外側にあった観賞用の船形埴輪のレプリカを撮影してみました。
実物の船形埴輪をじっくり眺めてみると、表面のくぼみに赤色の塗料がほんのり見てとれます。赤色の塗料はベンガラというものだそうですよ。このことから造られた当時の船形埴輪は赤色に塗られていたと考えられているようです。赤い船形埴輪です。何だか幻想的ですよね。
解説書にはこうありました。“昔から、赤色には「神聖なものを護り、邪悪なものを退ける」力があると考えられてきました。船形埴輪に塗られた赤色は、宝塚古墳に葬られた人物の魂が何者にも邪魔されず黄泉の国【死後の世界】へ旅立つことができるようにとの願いが込められていたのかもしれません”
ここから、魂は邪悪なものに邪魔されながら、黄泉の国へ向かうのだという思想が、5世紀の初頭からあったのだなあと推測されます。だからこそ、大切な自分たちの王様の魂を、安全に黄泉の国へ送り届けたいという一心で、ベンガラを塗った大きな船形埴輪を造ったのでしょう。
ところで、埴輪って何?という疑問が湧いてきました。少し調べてみると、埴輪は古墳の上や周囲に並べた主に素焼きの焼き物のことで、死者の魂を守ったり鎮めたりするものと考えられているようです。別の説では、死後の世界をあらわしたものと捉えている学者もいるとのことですよ。
今も昔も、死後の世界はどのような世界かはっきりわかりません。さっきまで呼吸をしていた温かな体が、死を迎えることでどんどん冷たくなり、腐食が始まる・・・。そして、最後は骨だけになるという形態変化が目の前で起きるわけです。おそらく当時の人にとっては死は恐怖でしかなかったと思います。だからこそ、死後の世界では、豊かに暮らしてほしいと願い、埴輪という捧げ物をしたのかもしれませんね。
そんな死後の世界を想像した、船形埴輪の観賞でした。興味のある方は、松阪市文化財センター(はにわ館)へ足をお運びくださいませ。
with k 4E